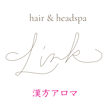東京都で2025年11月にインフルエンザの流行警報が発表されました。11月中に流行警報が発表されるのは16年ぶり、2009年以来となります。毎年、この季節になるとさまざまな感染症が流行しますが、そもそも、なぜ秋から冬にかけて私たちの免疫力は低下してしまうのでしょうか?
漢方の世界では、秋〜冬は「肺」の働きが弱くなりやすい季節とされ、呼吸器や免疫機能にも影響が出ると考えられています。そして、免疫が低下する背景には必ず「疲労」が存在します。
では、この季節の疲労の原因はどこにあるのでしょうか?その大きな要因のひとつが “乾燥” です。気温が下がり空気が乾燥してくると、肌がカサつきやすくなるだけでなく、喉・鼻・口・気管などの粘膜もダメージを受け、防御機能が弱まります。「肌が乾燥すると疲れやすい」「秋冬になった途端、眠っても疲れが抜けない」――そんな経験はありませんか?実は乾燥は、ただの季節的トラブルではなく、体にとってストレスとなり、徐々に疲労を蓄積させ免疫機能を弱らせる原因になるのです。
何故、乾燥が疲労を招くのか?
① 血液の濃度が上がってしまう
体内の水分が不足すると、血液が濃くなり流れが悪くなります。血液循環が滞ると酸素や栄養素が細胞まで届きにくくなり、老廃物や疲労物質の排出もスムーズにいきません。結果として、体のあちこちに疲れが溜まりやすくなります。
② エネルギーを生み出すのにも水分が必要
私たちの体は、水分を使って栄養素からエネルギーを作り出しています。体内の水分が足りないと、エネルギー生成が効率よく行えず、疲労感が増す原因になります。水分は単なる飲み物ではなく、生命活動に欠かせない材料なのです。
③ 乾燥で交感神経が優位に
体が乾燥すると、体は水分を守ろうと警戒モードに入ります。すると自律神経のうち交感神経が優位になり、緊張状態が続きます。これにより心身のリラックスが妨げられ、休息しても疲れが取れにくくなるのです。
④ 乾燥で体温調整がうまくいかない
水分不足は汗や呼吸による体温調整にも影響します。体温を適切に調整できなくなると、手足の冷えや筋肉のこわばりが起こりやすく、これも疲労感を増幅させる要因になります。
乾燥疲労を防ぐ3つの養生法
では、どうすればこの季節の乾燥による疲労や免疫低下を防げるのでしょうか?ここからは実践できるケア方法をご紹介します。
① 身体を「潤す食事」を取り入れる
秋〜冬の食養生では、「潤い」を補う食材を選ぶことが大切です。
おすすめ食材:
梨・りんご
大根・れんこん
白きくらげ
黒ごま
はちみつ
豆乳・味噌・納豆
松の実・くるみ
特に梨やれんこんは肺を潤し、咳や乾燥の症状に良いとされています。
② 呼吸と姿勢で肺をサポートする
乾燥した季節は呼吸が浅くなりがちです。深呼吸は酸素供給だけでなく、自律神経の調整にも役立ちます。ポイントは「細く長く吐く」こと。吐き出す量が増えることで自然に吸気が深まります。
③ 香りを使って自律神経と免疫にアプローチ
嗅覚は脳の本能的な領域にダイレクトに作用するため、疲労やストレスによる免疫低下に非常に有効です。
特に漢方アロマでは、
呼吸が深まる
気(エネルギー)が巡る
緊張がゆるみ、回復力が高まる
といった効果が期待できます。
乾燥で鈍くなった体の感覚をリセットし、本来のバランスを取り戻すサポートになります。
秋から冬にかけて免疫が低下するのは、偶然ではありません。乾燥が体に負担をかけ、疲労が積み重なり、結果として免疫力が低下するーーこれが季節性の体調不良の大きなメカニズムです。だからこそ、この季節は 潤いを守り、呼吸を整え、体の声に耳を傾けることが大切です。漢方の世界では秋冬は陰の季節となり、本来であれば活動量を減らし睡眠時間などを増やして休息に重点を置くべき期間となります。イベントなども多くなるこれからの時期、楽しみつつも無理をせず、養生ありきで日々を過ごしていきたいですね。