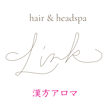養生
養生 · 2026/02/13
食養生における注意点 食養生を実践するうえで最も大切なのは、「何が良い・悪い」という固定的な価値観ではなく、その方の体質・体調に合っている かどうかを基準にすることです。 漢方では、食材にはそれぞれ「寒・熱・温・涼」といった性質や、五味(酸・苦・甘・辛・鹹)などの働きがあると捉えます。そ...
養生 · 2026/01/25
前回の記事では「食養生の基本のき」として、体を整えるための土台となる考え方をお伝えしました。 今回はその続きとして、今日からすぐに実践できる食養生についてお話しします。 内容自体は、どこかで一度は聞いたことのある、とてもシンプルなものです。 しかし、シンプルであるがゆえに軽視されやすく、同時に最も効果的で重要な養生法でもあります。...
養生 · 2025/12/20
― 現代生理学から紐解く、養生の知恵 ― 前回の記事 「先人達の観察眼 〜骨と腎〜」 では、 東洋医学において「腎」が骨や成長、 老化と深く関わると捉えられてきた 背景を、現代医学の視点から考察しました。 今回はその第二弾として、 腎と泌尿器系の関係 に焦点を当て、 先人達の洞察がいかに理にかなっていたのかを、...
養生 · 2025/09/22
ここへきて気温が下がりはじめ、体調を崩される方が増えています。特に「疲労感」「風邪」「咳」「アレルギー症状」などを訴える方が多く、季節の変化が心身に影響を与えていることを実感します。...